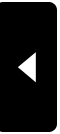2020年10月09日
リニューアル・ピアノコンサート〜ベートーヴェン ソナタ。。。
『やぶや森の中の道を、そして岩の上を歩くことの出来る自分を、この上もなく仕合せに思います。私のように自然を愛するものはないでしょう。森よ、木よ、そして岩よ、人生が欲するもっとも大きな「こだま」を恵たまえ。しかし私のみじめな聞こえない耳も、ここでは少しも苦になりません。どの木も自分に向かって、”聖なるかな”と讃えているようです.....』
1809年 ベートーベンがマルファッティー夫人に宛てた手紙から(世界音楽全集7 ベートーベン2)

ルッチプラザ で開催の「リニューアル・ピアノコンサート」まで1週間度となりました。
連日の弾き込みも1ヶ月をすぎ、今週はピアノ庫からホールのステージに移動して、出演者のお二人と、音色や音量についてお話ししました。
今回のコンサート企画では、ベートーヴェン、ショパン、ラフマニノフにターゲットを当て、2人のピアニストさんに曲を選んで頂きました。
今年12月に生誕250年を迎えるベートベンは、33曲ものピアノソナタ(番号のついているもの)を作曲しました。このことは、ベートーベンが活躍した19世紀前半、ドイツ、フランス、イタリアなどで職人たちが競って新しいピアノを発表し、音域・音色・ペダルなど進化を遂げた時代であったことが背景の一つとしてあげられます。

《48歳、耳が聞こえなくなったベートーヴェンが、後期のソナタを作曲した際使用していたロンドンの製作者によるピアノ》
(世界音楽全集7 ベートーベン2)
ここで裏話ですが・・・
まだ記憶に新しい、音楽企画湖音が企画した3年連続コンサート「エンジョイ・シリーズ」。
第2回目の「古典派」の際に、私はオール・モーツァルトでプログラムを組みました。
「古典派といえば、ベートーベンでは?」
という声もありましたが、私自身、ベートーベンを「古典派」というくくりの中にとどめたくない思いがありました。
確かに、伝統や形式を維持した理念は古典的と言えるのですが、ベートーヴェンの心にあったロマン主義は、確実に19世紀の作曲家に受け継がれたと思えるのです。
私の中で「ロマン派の出発点」であるベートベンのピアノソナタを、今回のような形でコンサートプログラムに組み込めたことは、とても幸せなことです。

《初期のソナタを作曲していた頃住んでいたハイリゲンシュタットの家》
10月17日のリニューアル・ピアノコンサートの第1部は、ベートヴェン ソナタ第14番 嬰ハ短調 作品27-2「月光」第1楽章アダージョ・ソステヌート 第2楽章アレグレット 第3楽章プレスト・アジタート(演奏:竹中直美さん)と、ソナタ第8番 ハ短調 作品13「悲愴」第1楽章グラーヴェ・アレグロ・ディ・モルト・エ・コン・ブリオ 第2楽章アダージョ・カンタービレ 第3楽章ロンド・アレグロ(演奏:平居妙子さん)を演奏して頂きます。
第14番 は「月光」として知られるソナタですが、ベートーヴェン自身が「ファンタジア風ソナタ」と記している通り、ファンタジア(幻想曲)の趣きが濃い作品です。また、「月光」と同様、改良された68鍵盤のピアノを使用していた初期の傑作として知られる第8番 は、初期の傑作と言われるもので、第14番「月光」第23番「熱情」とならんで三大ピアノソナタと呼ばれています。
”聖なるかな”という作曲家の心を、お楽しみいただければ幸いです。
★次回は第2部 ショパンについてお伝えします★
ベートーヴェンのソナタといえば・・・
大学受験の副科ピアノ。
第5番 ハ短調 10-1を、毎日毎日弾き続けました。
「なんて綺麗なんだろう・・・なんてドラマティックなんだろう・・・」
と本科の練習の三倍は時間をかけていた日々を思い出します。。。
大学受験の副科ピアノ。
第5番 ハ短調 10-1を、毎日毎日弾き続けました。
「なんて綺麗なんだろう・・・なんてドラマティックなんだろう・・・」
と本科の練習の三倍は時間をかけていた日々を思い出します。。。