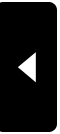2022年03月07日
小鳥のように
小鳥は美しい声でうたう。
小鳥はその愛らしさで人の心を救う。
小鳥は欲もなく嘘もない。
子供の頃は「正直になりなさい。」と教えられる。
大人になると「言って良いことと悪いことがある。」と窘められる。
いつのまにかずるい自分になっていることに気付いた時、小さな小さな命の尊さに涙する。
人は小鳥のようにはなれない。
あまりにも当たり前の現実に、今更のように涙する。
2022年01月10日
玉樹の花は開く、白砂に、清らかに。
玉 樹
雪 山 万 重 鎖 僊 郷
玉 樹 花 開 隔 渺 茫
白 石 青 苔 明 月 上
幾 生 修 得 掬 霊 香
〜岡倉寛三(天心)がブリヤンダバに送った漢詩〜

玉樹
人跡の踏むを許さぬ断崖のかなた、ヒマラヤの氷の胸に安らかに抱かれて
玉樹の花は開く、白砂に、清らかに。
くりかえしくりかえし、幾つの生を重ねつつ
恍惚たる幻境のなか、月光照らす石上の
冷たい苔に坐らねばならないのだろう、
いやはてに ー くまなく霊は浄められ、
聖なる花の香しい露を啜るそのときまで。
〜岡倉寛三(天心)の英訳を元に大岡信が訳〜
その人が、自分にとってかけがえなく清らかで、
手の届かない次元の世界にいても、
力強く、決してあきらめることなく・・・
共に清らかに生きようとする勇気を、わずか二十八の漢字が語っている。。。
2022年01月09日
心如淵泉、2022年を迎えて。。。
『心如淵泉』
ー 心深い泉の如く深く落ち着いている ー
22年、新年を迎え、ありがたき書の文字に出会った。
ひこね文化デザインフォーラム主催の「文化サロン〜四方山談義」は今日が第1回目。
書家の松宮忠夫先生のテーマ「文字(言葉)を書くことで自分を掘る」は、「私の昨年の言葉」を深く考えるきっかけとなった。
言葉は心とリンクしている。
この歳になると、いやでもそれが見えてしまう。
リズムよく綺麗な言葉を並べると、耳には心地よいが心に入ってこない。
誠実でいようとすると、時に誤解を招く。
言葉はいつも重要なキーワードとなる。
人と繋がることは面倒で、だけれど、それ以上にあたたでありがたい。
私は人が好きだ。
言葉が好きだ。
だから、歌が好きなのだとおもう。
大好きな着物を、しばらく着なかった。
大好きな歌も、昨年は十分の一も歌わなかった。
家に帰って、深呼吸して書いて見た。
『心如淵泉』。
世の中が色を変えても、変わらない自分でいるために。
新しい年をスタートさせよう。。。
2021年11月02日
秋の子ねこ。。。
だれを待っていたの?
そんな狭いところで。
だれを呼んでいたの?
消えそうな声で。。。
あなたを捨てた人?
あなたを愛した人?
あなたが愛した人?
かわいい子猫はだれからも愛される。
か細い声はだれもが守ってくれる。
おこってはダメ。
あらびてはダメ。
そこを離れてはダメ。
そこで待っていなければ、、、ダメ。
2021年10月25日
愛情のおにぎり。。。
母の握ったおにぎりを、最後に食べたのはいつだったろう。

握った人の元気をもらえる魔法のおにぎり。
上手なにぎり方は母から教わった。
力の入れ方で、ご飯の美味しさが変わるなんて、最初は信じてなかったけれど、未だに母のおにぎりは私の中で1番だ。
食べてくれる人がいるから頑張れる。
その人の元気は、私を元気にしてくれる。
それは歌と同じだ。

イクラとアナゴと青菜ジャコのおにぎりは大人の味。
梅干しと甘い煎り卵とシャケのおにぎりは母の味。
自分で握ったおにぎりは、悲しいけれど元気は出なかった。。

母の握ったおにぎりを最後に食べたのは6年前。
50年間の母のおにぎりの中で、一番美味しいおにぎりだった。。。
2021年09月16日
命といふもの〜堀文子 画文集。。。
堀文子さんの追悼展『スケッチと本画でたどる人と芸術』第2期が8月21日から9月20日まで、名都美術館で開催されている。
私が堀文子さんの絵をはじめて目にしたのは、ちょうど大学受験の頃、料理好きの母が持っていたNHK料理番組のテキスト『きょうの料理』の表紙絵だった。
母は「書き込む人」だったので、アヤメの絵の表紙や、気になるページには何やら食材や栄養素の書き込みがあり、新聞の切り取りなども何枚かはさまれていた。
今思うと、サイドボードの上のそのテキストは、料理の本というよりは、母の忘備録帳だったのだ。
40年近くたった今、私はその絵を描いた人が堀文子さんだったと知った。
追悼展に行けなかったが、私の手元には画文集「命といふもの 第2集」が届いた。

花木と共に・・・と記された、ヤマブキ・筍・蓮根の優しい表紙をめくると、私が愛するとり「ジョウビタキ」の絵と、ジョウビタキを神の使いと表現した堀綾子さんの文が心に刺さった。
「花を愛でる人は鳥も愛でる。」
そんな自分の勝手な思い込みが真正面から肯定されたような気がして、1行ずつ、子供のように指で文字をたどりながら、何度もなんどもジョウビタキの項を読んだ。

一気に読んでしまうのは、もったいない画文集。
私は1日に1項ずつ楽しむことにした。
ボロボロのアヤメのテキストを、私がお嫁に行くまでずっと持っていた母に、この画文集を見せてあげたいと、ふと思った。
母の「ちぎり絵」に、よく似た作品があったのを思い出した。
母はきっと、あのテキストのアヤメが大好きだったのだろう。。。
2021年08月15日
れんげ畑と、幼い私と、歌と。。。
「れんげ草」という詩に出会って 白谷仁子
私が生まれ育った滋賀県長浜市は、山、川、そして湖の恵みを受ける自然豊かな街です。
小学1年生から大学を卒業するまで、私は琵琶湖の畔でのびのびと暮らしました。
家から歩いて数分のところには、新興住宅地のために整備された埋立地が広がっており、桜の時期が終わると、そこは目を見張る一面のれんげ畑が広がりました。
小学校から帰ると一目散にそこへ向かい、雨の日も晴れの日も、れんげの花に囲まれて無心に遊びました。
琵琶湖の水面にお日様が沈む頃、エプロン姿の母が迎えに来てくれて、暗くなるまで冠や首飾り、指輪をいっしょに作りました。
「れんげ姫さん、そろそろ帰ろっか。」
母の言葉は「おしまい」の合図。
夕日を背に、母と私は大きな声で歌をうたいながら家へと帰って行きました。
今、たくさんの家が立ち並ぶその場所は、母と私の「れんげ畑」の思い出の場所です。
藤岡きみこさんの詩「れんげ草」と出会い、母との絆や、幼い頃の思い出に再び触れることができました。
今は施設でお世話になっている母にも、この歌を届けたいと思っています。
〜全日本児童音楽協会『新しい子どもの歌 2021』ハンナ出版より〜
『童謡』『童謡歌手』
今や,ひと昔前の言葉のように感じる言葉。
物心ついてからというもの、母の歌う童謡や叙情歌を聴きながら育った私は、日々の時間が歌と共にゆっくりとながれていました。
子どもの歌を、子どもが、子どもらしく歌う。
大人は子どもの感性や情緒、優しさを育てるために詩を書き、作曲家は同じ気持ちでメロディーをつけました。
童謡運動の幕開けから100年以上が経った今、消してはいけない日本の音楽分野があることを、私たちはわすれてはいけません。
藤岡きみこさんの詩『れんげ草』を読んだ時、驚きと懐かしさで、ほとんど瞬間的にメロディーが心に浮かびました。
まさに、私の大切にしている母との思い出そのものだったから。
全日本児童音楽協会が開催した第66回『新しい子どもの歌コンサート』は8月5日に開催され、私の作曲した『れんげ草』(作詞:藤岡きみこ 作曲:白谷仁子)は小学校4年生の馬場眞実さんの独唱で発表されました。
その1週間後、『れんげ草』を気に入ってくれた眞実さんは、12日・13日と開催された『あおいコンクール』でも歌ってくださり、見事1位に輝きました。
童心に帰る・・・
それは、何気ない瞬間にふと心に降ってくる小さな光の粒のように・・・
童謡は心のふるさと。
忘れていた何かを思い出させてくれます。
小学校入学と同時に、私は大好きだった長浜市のまちなかから、琵琶湖のほとり移り住んだ。父が家族の為に設計し、建ててくれたその家の周りには、それまで暮らしたまちなかには無い風景があふれていた。まだ数件しか建っていない団地のあちこちにある桑畑。埋立地一面に広がるレンゲ畑。家から僅か数分歩くと、そこには広大な琵琶湖が両手をひろげていた。当時、好奇心旺盛だった私にとってそれは、まさに『自然の楽園』だった。
2014年 滋賀県建築設計家協会 鳰の巣vol.40『淡海に寄せる歌〜白谷仁子』から
2021年07月31日
音楽と公民館と。。。ルッチプラザ『第41回りれーピアノ発表会』
今日、7月31日は米原市のルッチプラザで、第41回りれーピアノ発表会が開催された。
大学を卒業してすぐ、中学校の常勤講師をしながら、実家でピアノやソルフェージュを教えるという音楽教室をはじめた。
それから30年あまり、結婚して拠点を移し、子育て中も休まずに続けてきた。
演奏活動でいっぱいいっぱいの時期も、発表会は全て自主公演してきた。
多い時で50名を超える生徒が出演した年もあった。
今ではその思い出全てが宝物だ。
地域には良い楽器を備えた音響の優れたホールがあちこちにある。
ルッチプラザは、自身の初のソプラノリサイタルから、ホームグラウンドのように親しんできた。
ピアノはスタインウェイ。
昨年、オーバーホールの時には、弾きこみ(音が安定するまでスケールなどを定期に行い調律師と連携を図りながら、ステージに送る準備をする)からお披露目コンサートまで湖音として関わらせてもらった。
市からご理解をいただいたことは、私たち地域で活動するものにとって、とても喜ばしいことだった。
今年は初めて、りれーピアノ発表会に生徒3名を出すことにした。
昨年から2年続けて湖音の発表会が中止となり、部活や勉強との両立の中で頑張っている生徒の発表の場として、とても良いタイミングだった。
ルッチプラザは米原市の公民館としての機能だけでなく、アマチュアからプロの海外アーティストまで、他種のコンサートを開催してきた。
「世界で活躍するピアニストが弾くピアノを、同じホールで弾ける。」
こんな贅沢が身近にあるのは、ピアノを習っている子供達にとって、とても幸せなことだ。
コンサートや発表会だけでなく、安価で借りれることから、ホールとスタインウェイを借りて練習に使用している子もいる。
発表会といえば、いつもは走り回っているが、今日はかわいい生徒たちの演奏を、ゆっくりと客席で聴く事が出来た。
公民館として、市がホールや高価な楽器を維持することは大変な事だ。
本来なら、地域性を図り、それに担ったハコ(ホール)や楽器を揃えて、地域での活用に生かすことが大切だが、何年か前、市町の統廃合が行われたあたり、贅沢なホールがあちこちに建設された。
ルッチプラザは客席300あまりの音楽ホールだ。
残響も、音の飛ぶ早さも、クラッシック音楽には最適だと思う。
でも敷居は決して高くなく、利用者をいつも大切にしてくれる。
ホールの個性を守りながら、地域と密接に音楽教育をコツコツと続けている姿は、私たち地域の音楽家の誇りだ。
ここで一流のピアノに触れ、地域と育った子どもたちがまた、音楽の裾野を広げてくれることを祈ろう。

椿ちゃん「アレグロ 変ロ長調K3・アンダンテ へ長調K616」
愛友ちゃん「乙女の祈り/バダジェフスカ」
堅士くん「野ばらに寄す/マクダヴェル」「真夜中の火祭り/平吉穀州」
ありがとう。
先生がいつも言っていること、「自分の音を聴く」。
当たり前だけど、とても難しいこと。
今日の音、とてもきれいだった。
また一歩一歩、ゆっくり前へ進もう。
続きを読む
2021年07月28日
虫のこえとバロックと。。。2017年9月
『ゴールドベルク変奏曲のアリアが始まると、虫は一斉に静まり、
ついでイタリア協奏曲になると、スィッチョンの声がどこからか聞こえ出し、
平均律に入ると、ツクツクボーシが賑やかに歌い出しました。
・・・わかるんですね、虫さんにも音楽が・・・』
こんなMCをしながら、米原市にある石田三成ゆかりの観音寺境内で、バロックコンサートが開催されてから、もうすぐ4年が経つ。
これは、米原市と私の主宰する音楽企画湖音との企画で、滋賀県アートコラボレーション事業の一環として、本公演となる翌年開催のホールコンサート『エンジョイ・ザ・バロック』の前に、3回のアウトリーチコンサートを行うというものだった。
アウトリーチコンサートとは、演奏家がときに楽器を持参して地域を訪問する、いわば出前コンサートのことだ。
スタートは、チェンバロとソプラノによるバロック音楽のプログラム。
おそらく、会場となった観音寺にチェンバロが運び込まれたのは、長い歴史の中でも初めてのことだろう。
チェンバロ奏者 小林祐香さん(吉田祐香さん)の美しいチェンバロで歌えるという、私にとって幸せな時間でもあった。。。
《モンテヴェルディ「苦しみが甘美なものならば Si dolce è'l tormento, SV 332.」

開け放された板戸と障子、まるで山全部がホールと化した中で、虫の声も歌声もともに溶け込んでいく瞬間が心地よかった。

お寺DEコンサート〜バロックの調べ〜
2017年9月24日(日)13:00開演(12:30開場) 観音寺
ープログラムー
G.F.ヘンデル
樹木の影で 調子の良い鍛冶屋
A.スカルラッティ 1660-1726
オペラ「十人委員会の凋落(ちょうらく)」から
貴方が私の死の栄光を
C.モンテヴェルディ1567-1643
苦しみはかくも甘き
J.S.バッハ 1685-1750
ゴールドベルク変奏曲よりアリアBWV988
イタリア協奏曲BWV971 3楽章
A.ヴィヴァルディ1678-1741
歌劇「ジュスティーノ」から
喜びと共に会わん
J.S.バッハ
平均律ハ長調プレリュードBWV846
J.S.バッハ/C.グノー
Ave Maria
ソプラノ 白谷仁子 チェンバロ 小林祐香
《2017年9月 チェンバロの説明をする祐香さん》

演奏後は、祐香さんの提案で楽器説明を間近で受けることもでき、チェンバロを取り囲むお客様が途絶えることなく続いた。
『ゴールドベルク変奏曲のアリアが始まると、虫は一斉に静まり、
ついでイタリア協奏曲になると、スィッチョンの声がどこからか聞こえ出し、
平均律に入ると、ツクツクボーシが賑やかに歌い出しました。』

・・・わかるんですね、虫さんにも音楽が・・・
ついでイタリア協奏曲になると、スィッチョンの声がどこからか聞こえ出し、
平均律に入ると、ツクツクボーシが賑やかに歌い出しました。
・・・わかるんですね、虫さんにも音楽が・・・』
こんなMCをしながら、米原市にある石田三成ゆかりの観音寺境内で、バロックコンサートが開催されてから、もうすぐ4年が経つ。
これは、米原市と私の主宰する音楽企画湖音との企画で、滋賀県アートコラボレーション事業の一環として、本公演となる翌年開催のホールコンサート『エンジョイ・ザ・バロック』の前に、3回のアウトリーチコンサートを行うというものだった。
アウトリーチコンサートとは、演奏家がときに楽器を持参して地域を訪問する、いわば出前コンサートのことだ。
スタートは、チェンバロとソプラノによるバロック音楽のプログラム。
おそらく、会場となった観音寺にチェンバロが運び込まれたのは、長い歴史の中でも初めてのことだろう。
チェンバロ奏者 小林祐香さん(吉田祐香さん)の美しいチェンバロで歌えるという、私にとって幸せな時間でもあった。。。
《モンテヴェルディ「苦しみが甘美なものならば Si dolce è'l tormento, SV 332.」
開け放された板戸と障子、まるで山全部がホールと化した中で、虫の声も歌声もともに溶け込んでいく瞬間が心地よかった。
お寺DEコンサート〜バロックの調べ〜
2017年9月24日(日)13:00開演(12:30開場) 観音寺
ープログラムー
G.F.ヘンデル
樹木の影で 調子の良い鍛冶屋
A.スカルラッティ 1660-1726
オペラ「十人委員会の凋落(ちょうらく)」から
貴方が私の死の栄光を
C.モンテヴェルディ1567-1643
苦しみはかくも甘き
J.S.バッハ 1685-1750
ゴールドベルク変奏曲よりアリアBWV988
イタリア協奏曲BWV971 3楽章
A.ヴィヴァルディ1678-1741
歌劇「ジュスティーノ」から
喜びと共に会わん
J.S.バッハ
平均律ハ長調プレリュードBWV846
J.S.バッハ/C.グノー
Ave Maria
ソプラノ 白谷仁子 チェンバロ 小林祐香
《2017年9月 チェンバロの説明をする祐香さん》

演奏後は、祐香さんの提案で楽器説明を間近で受けることもでき、チェンバロを取り囲むお客様が途絶えることなく続いた。
『ゴールドベルク変奏曲のアリアが始まると、虫は一斉に静まり、
ついでイタリア協奏曲になると、スィッチョンの声がどこからか聞こえ出し、
平均律に入ると、ツクツクボーシが賑やかに歌い出しました。』

・・・わかるんですね、虫さんにも音楽が・・・
2021年07月12日
ポートレート。。。
わたしらしい。
わたしらしくない。
あなたらしい。
あなたらしくない。
「らしさ」って、自分が作るもの?
それとも、知らないうちに育てられていくもの?
《Photo スタジオ・エコール》
自分のことはずっとナゾだった。
ナゾだからおもしろかった。
自分と付き合っていくことがおもしろかった。
着るものも髪型も、人がどう思うかは関係なかった。
答えを出すのは簡単。
「好き」か「好きでない」か。
15年ぶりに、髪を短くした。
「長い髪を束ねられなくなった」から。
見慣れない自分に出会えることも、「生きている」からこそかもしれない。
ポートレートのわたしは、まぎれもなく「わたしらしい」私だから。。。