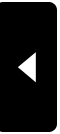› 音楽企画湖音ko-on 白谷仁子のブログ「音・人・里」 › 地域活動
› 音楽企画湖音ko-on 白谷仁子のブログ「音・人・里」 › 地域活動2020年10月12日
リニューアル・ピアノコンサート〜ショパン。。。
切り離された絵。
一枚はパリのルーブル美術館。
もう一枚はコペンハーゲンのオードルップゴー美術館。
十代の私にとって、ショパンとジョルジュサンドの恋は、遠い大人の世界の物語だった。
お小遣いで買った「音楽の手帳 ショパン」(青土社)を隅から隅までなんども読んでいるうちに、いつの間にかグラビアのドラクロアが描いたショパンが、「私のChopin」となった。。

早朝、食事も早々にホテルを出て、セーヌ川沿いを楽しみながら歩いた。
フランスパンを小脇に挟んだ紳士、朝の散歩を楽しむ老夫婦。
全てが景色に溶け込んでいた。
次第に早足になる私の心は、もちろんルーブル美術館の一枚の絵。

《早朝のセーヌ川》
今回のコンサート(17日 リニューアルコンサート)第2部の始まりは、ショパンの「ノクターン第8番変ニ長調 作品27-2」(演奏:平居妙子さん)。
この作品は1835年、ショパンが25歳の時の作品。
ショパンが両親とカルロヴィ・ヴァリ(カールスバード)で5年ぶりに再開し、3週間ほど共に過ごせた幸せな年だった。
21歳で祖国ポーランドを離れ、パリで暮らしたショパン。
祖国への強い思いが、今も世界中の人を魅了し続けるのではだろうか。

ショパンと「唯一無二の友情」と言われる画家ウジェーヌ・ドラクロワ。
肖像画の少ないドラクロアがショパンを描いたのは、ピアニスト・作曲家であるショパンなのか、それとも友人ショパンなのか、聞いてみたい気がする。

2部の第2曲目は、ノクターン第8番から10年後の35歳の時からとりかかり、翌年に完成させた「幻想ポロネーズ 変イ長調作品61」(演奏:平居妙子さん)。
そのころの体調や精神状態を知ると、「最後の大曲」と言われる名曲を生み出したエネルギーの根源は何なのかとても興味深く感じるのだ。
リニュアル・コンサートの日、10月17日は、ショパンが永遠の眠りについた日である。
後日の葬儀には、モーツァルトのレクイエムによるミサ、最後までそこに立ち会ったドラクロワがいた。
遠い遠い存在の作曲家の作品を愛し、その生き方に共感したり、涙したり・・・
再現者である私たちは、与えてもらうばかりでなく、作曲家に誠実さを持って感謝を返さなくてはならないとおもう。
それは楽器に対しても同じ。
ピアノとショパン。
魅了され続けて40年が過ぎた。
その言葉の響きは、今も心を熱くしてくれる。
続きを読む
一枚はパリのルーブル美術館。
もう一枚はコペンハーゲンのオードルップゴー美術館。
十代の私にとって、ショパンとジョルジュサンドの恋は、遠い大人の世界の物語だった。
お小遣いで買った「音楽の手帳 ショパン」(青土社)を隅から隅までなんども読んでいるうちに、いつの間にかグラビアのドラクロアが描いたショパンが、「私のChopin」となった。。

《2020年 冬 パリ「ルーブル美術館」にて撮影》
早朝、食事も早々にホテルを出て、セーヌ川沿いを楽しみながら歩いた。
フランスパンを小脇に挟んだ紳士、朝の散歩を楽しむ老夫婦。
全てが景色に溶け込んでいた。
次第に早足になる私の心は、もちろんルーブル美術館の一枚の絵。

《早朝のセーヌ川》
今回のコンサート(17日 リニューアルコンサート)第2部の始まりは、ショパンの「ノクターン第8番変ニ長調 作品27-2」(演奏:平居妙子さん)。
この作品は1835年、ショパンが25歳の時の作品。
ショパンが両親とカルロヴィ・ヴァリ(カールスバード)で5年ぶりに再開し、3週間ほど共に過ごせた幸せな年だった。
21歳で祖国ポーランドを離れ、パリで暮らしたショパン。
祖国への強い思いが、今も世界中の人を魅了し続けるのではだろうか。

ショパンと「唯一無二の友情」と言われる画家ウジェーヌ・ドラクロワ。
肖像画の少ないドラクロアがショパンを描いたのは、ピアニスト・作曲家であるショパンなのか、それとも友人ショパンなのか、聞いてみたい気がする。

2部の第2曲目は、ノクターン第8番から10年後の35歳の時からとりかかり、翌年に完成させた「幻想ポロネーズ 変イ長調作品61」(演奏:平居妙子さん)。
そのころの体調や精神状態を知ると、「最後の大曲」と言われる名曲を生み出したエネルギーの根源は何なのかとても興味深く感じるのだ。
リニュアル・コンサートの日、10月17日は、ショパンが永遠の眠りについた日である。
後日の葬儀には、モーツァルトのレクイエムによるミサ、最後までそこに立ち会ったドラクロワがいた。
遠い遠い存在の作曲家の作品を愛し、その生き方に共感したり、涙したり・・・
再現者である私たちは、与えてもらうばかりでなく、作曲家に誠実さを持って感謝を返さなくてはならないとおもう。
それは楽器に対しても同じ。
ピアノとショパン。
魅了され続けて40年が過ぎた。
その言葉の響きは、今も心を熱くしてくれる。
続きを読む
2020年10月09日
リニューアル・ピアノコンサート〜ベートーヴェン ソナタ。。。
『やぶや森の中の道を、そして岩の上を歩くことの出来る自分を、この上もなく仕合せに思います。私のように自然を愛するものはないでしょう。森よ、木よ、そして岩よ、人生が欲するもっとも大きな「こだま」を恵たまえ。しかし私のみじめな聞こえない耳も、ここでは少しも苦になりません。どの木も自分に向かって、”聖なるかな”と讃えているようです.....』
1809年 ベートーベンがマルファッティー夫人に宛てた手紙から(世界音楽全集7 ベートーベン2)

ルッチプラザ で開催の「リニューアル・ピアノコンサート」まで1週間度となりました。
連日の弾き込みも1ヶ月をすぎ、今週はピアノ庫からホールのステージに移動して、出演者のお二人と、音色や音量についてお話ししました。
今回のコンサート企画では、ベートーヴェン、ショパン、ラフマニノフにターゲットを当て、2人のピアニストさんに曲を選んで頂きました。
今年12月に生誕250年を迎えるベートベンは、33曲ものピアノソナタ(番号のついているもの)を作曲しました。このことは、ベートーベンが活躍した19世紀前半、ドイツ、フランス、イタリアなどで職人たちが競って新しいピアノを発表し、音域・音色・ペダルなど進化を遂げた時代であったことが背景の一つとしてあげられます。

《48歳、耳が聞こえなくなったベートーヴェンが、後期のソナタを作曲した際使用していたロンドンの製作者によるピアノ》
(世界音楽全集7 ベートーベン2)
ここで裏話ですが・・・
まだ記憶に新しい、音楽企画湖音が企画した3年連続コンサート「エンジョイ・シリーズ」。
第2回目の「古典派」の際に、私はオール・モーツァルトでプログラムを組みました。
「古典派といえば、ベートーベンでは?」
という声もありましたが、私自身、ベートーベンを「古典派」というくくりの中にとどめたくない思いがありました。
確かに、伝統や形式を維持した理念は古典的と言えるのですが、ベートーヴェンの心にあったロマン主義は、確実に19世紀の作曲家に受け継がれたと思えるのです。
私の中で「ロマン派の出発点」であるベートベンのピアノソナタを、今回のような形でコンサートプログラムに組み込めたことは、とても幸せなことです。

《初期のソナタを作曲していた頃住んでいたハイリゲンシュタットの家》
10月17日のリニューアル・ピアノコンサートの第1部は、ベートヴェン ソナタ第14番 嬰ハ短調 作品27-2「月光」第1楽章アダージョ・ソステヌート 第2楽章アレグレット 第3楽章プレスト・アジタート(演奏:竹中直美さん)と、ソナタ第8番 ハ短調 作品13「悲愴」第1楽章グラーヴェ・アレグロ・ディ・モルト・エ・コン・ブリオ 第2楽章アダージョ・カンタービレ 第3楽章ロンド・アレグロ(演奏:平居妙子さん)を演奏して頂きます。
第14番 は「月光」として知られるソナタですが、ベートーヴェン自身が「ファンタジア風ソナタ」と記している通り、ファンタジア(幻想曲)の趣きが濃い作品です。また、「月光」と同様、改良された68鍵盤のピアノを使用していた初期の傑作として知られる第8番 は、初期の傑作と言われるもので、第14番「月光」第23番「熱情」とならんで三大ピアノソナタと呼ばれています。
”聖なるかな”という作曲家の心を、お楽しみいただければ幸いです。
★次回は第2部 ショパンについてお伝えします★
続きを読む
2020年09月18日
おかえりなさい。ルッチプラザ「スタインウェイ 」。。。
米原市民交流プラザが2001年にオープンしてから、ずっと地域に、そして全国の演奏家達に愛されてきたピアノ”スタインウェイ” が、オーバーホールから帰ってきた。

《Photo studio école》
10月17日のコンサートを前に、9月の初めからスタインウェイ の弾き込みが始まり、出演者の竹中直美さん、平居妙子さん、そして、エンジョイコンサートでコーラス伴奏やジュニアオーケストラとの共演をしてきた澤村優子さん、私の4人が、かわるがわるに毎日ピアノ庫に通っている。
《9月18日(金曜日)》
その都度情報を共有しながら、次の調律までに、私は報告書をまとめている。
今まで、数え切れないほど共演してきたスタインウェイ の鍵盤を、これほどじっくり弾いたのは、私にとって19年来初めてのことだ。
私の場合、何時間もスケールを延々と引き続け、鍵盤の様子や音色に耳をすませ、地味でありながら心を「無」に、ただ「音」とだけ向き合える贅沢な時間を過ごしている。
《ハンマーにうっすらと溝が・・・》

息を止めて、そっと覗いてハンマーを見ると、うっすらと細い溝が確認できる。
「あとひと月で、どこまで変わるのだろう・・・」
そんなことを思いながら、時間の経つのを忘れる。
美しく威厳のある立ち姿の前に座っていると、自然と背筋が伸びる。
洋琴・・・カタカナよりも、そんな呼び名が似合うような気がするのは、私だけだろうか。
コンサートまでひと月。
共に歌える日が、ただ楽しみでたまらない。。。

「たくさんのお申し込み、ありがとうございました。8月いっぱいで予定の座席数は完了しました。当日は出演者一同心を込めて演奏いたします。特別企画”ジュニアによるピアノ演奏”のご紹介は次のブログにて。どうぞお楽しみに。」
続きを読む
2020年09月14日
いつまでも いつまでも〜立原道造 鮎の歌「物語」
僕には、たったひとつわからないことがある。
時はなぜこのようにくりかえすのか。
そしてなぜ僕にひきとめれずにすぐ死に絶え流のか。
立原道造全集第三巻 物語
鮎の歌「物語」からⅣ
9月になって、2つのコンサートに出かけた。
例年だと、週末は自分のコンサートやリハーサルが入っていて、月に2つのコンサートに出かけることは滅多とない私にとって、自分への良いプレゼントとなった。
6日、木之本スティックホールで開催された「Sous le Ciel de Paris」。
パリに留学されていたピアニスト 横田麻友子さんのお仲間と繰り広げるフランス音楽、日本の歌に、客席が始終引き込まれた。
プログラムも演奏も、流石だった。
コンサート中、4人のトークはパリのお話。。。
短い間だったが、2月にパリに滞在し、リサイタルを開催した私は、ほんのひと時、その空間を幸せな気持ちで共有した。
12日、びわ湖ホール大ホールで開催された「オペラ作曲家の横顔〜ロッシーニ〜」。
3月公演が中止となり、会場を小ホールから大ホールに変えての豪華なコンサートだった。
初期ロマン派のロッシーニのオペラはもちろんだが、宗教曲や合唱曲も大好きな私は心から楽しみにしていた。
お目当はもちろん第二部の「スターバト・マーテル」だった。
第一曲から十曲まで、時間を忘れて音楽と声とピアノを堪能した。
ホールの中にいると、音だけに集中できる。
演奏者である時も、聴衆者の時も、どちらでいても「自分」を鮮明に感じられる空間だ。
びわ湖ホールを後にしながら、耳に残る生きたハーモニーを感じながら思うことは一つだった。
練習を待つコーラスのメンバーを歌わせてあげること。。。
時は繰り返され、取り戻すことができない。
大切な時間は、大切に過ごすことで作られるものなのだということを、忘れてはいけない。

いつまでも いつまでも
いつまでも いつまでも
もしも 僕らが鳥だつたなら
空の高くを 飛んでゐよう
雲のあちらを あごがれながら
いつまでも いつまでも
木の枝にゐて うたつてゐよう
たつたひとつのしらべを
同じ聲で うたつてゐよう
身のまはりで すべてが死に
僕らのうたは 悲しみになる
そして 空は 限りなくとほい
あのあこがれは 夢だつた と
僕らの翼と咽喉は 誣ひるだらう
いつまでも そのあと いつまでも
鮎の歌「物語」からⅢ“いつまでも いつまでも”
立原道造全集第三巻 物語
続きを読む
2020年08月05日
Steinway &Sons リニューアル・ピアノコンサート♬
2001年3月、米原市民交流プラザがオープンしてから19年、市民のみならず国内・海外のアーティストに愛されて来た「素敵なピアノ」は、ルッチプラザ ベルホール310のシンボルとして、19年の間、美しい音色をホールいっぱいに響かせて来ました。
そのピアノ「スタインウェイ」は、8月から専門家のもとでオーバーホールされ、9月から専門家によって弾き込み作業を、そして10月17日に生まれ変わった音色を再びベルホールに響かせます。


今年生誕250年を迎えるベートーヴェンのソナタ「月光」「悲愴」、「スタインウェイのピアノは、すべてにおいて完璧」と賞賛したラフマニノフの「前奏曲」と言葉のない歌「ヴォカリーズ」他、リニューアルしたスタインウエイの音色をお楽しみください。
今年は県内でもたくさんのコンサート、発表会が中止となりました。
ルッチプラザ のスタインウェイも、そのことをとても残念に思っていたはずです。
年に一度のステージのために練習を積んで来た米原市内外のジュニアのみなさんのために、特別企画として、コンサート終了後にステージを設けることにしました。
詳しくは、チラシ裏面、または直接ルッチプラザ(0749-55-4550) にお問い合わせください。
どんなときも、「希望の灯(ひ)」「音楽の灯(ひ)」が、絶えないことを願っています。
2020年08月01日
歌声は愛敬の証。。。
梅雨明けを告げるように、
白くまぶしいサルスベリ。
ブドウのようにフサをつけ、
おしゃべり好きな女性のように、
サワサワ、サワサワと畑の中で歌う。。。
《サルスベリ 花言葉「愛敬」「おしゃべり」》

7月に再開したコーラス・ユウスゲ。
今日は2度目の練習日を迎えた。
今日私は、コーラス用に考えた自作フェイスシールドの紹介と、新しく取り組む素敵な曲集「小さないのち」(なかにしあかね )の練習を楽しみにしていた。
練習の後半、「集えなかった日々」「仲間と歌えなかった日々」について、1人ずつ気持ちを述べ合った。
話しているうちに、明るい声は涙声になっていった。
無理もないことだ。
車で自由に出かける事が出来、スマホやパソコンを使いこなせて、人の話し声は自由に聞き取れ、家に帰れば家族がいてくれる・・・
私にとっての「当たり前」が、「当たり前ではない」人たちがユウスゲには何人もいる。
月に2回のコーラスの場が、「血縁」ではなく「歌う事」で繋がる家族と過ごせる大切な場所なのだ。

母と同世代の女性たちにとっての「歌への想い」は、今の若者世代とも、私たちとも違う。
ユウスゲのメンバーから、私はその「歌の歴史」を知り、多くのことを学んできた。

真夏の日差しに負けることなく、仲良く房になって支え合い、風に揺れるサルスベリのように仲間と歌うことを生きがいにしている人たちがいる。
その心の輝きを、いつまでもいつまでも持ち続けて欲しい。。
白く眩しいサルスベリのように、愛敬の歌声を響かせながら。。。
続きを読む
白くまぶしいサルスベリ。
ブドウのようにフサをつけ、
おしゃべり好きな女性のように、
サワサワ、サワサワと畑の中で歌う。。。
《サルスベリ 花言葉「愛敬」「おしゃべり」》

7月に再開したコーラス・ユウスゲ。
今日は2度目の練習日を迎えた。
今日私は、コーラス用に考えた自作フェイスシールドの紹介と、新しく取り組む素敵な曲集「小さないのち」(なかにしあかね )の練習を楽しみにしていた。
練習の後半、「集えなかった日々」「仲間と歌えなかった日々」について、1人ずつ気持ちを述べ合った。
話しているうちに、明るい声は涙声になっていった。
無理もないことだ。
車で自由に出かける事が出来、スマホやパソコンを使いこなせて、人の話し声は自由に聞き取れ、家に帰れば家族がいてくれる・・・
私にとっての「当たり前」が、「当たり前ではない」人たちがユウスゲには何人もいる。
月に2回のコーラスの場が、「血縁」ではなく「歌う事」で繋がる家族と過ごせる大切な場所なのだ。

母と同世代の女性たちにとっての「歌への想い」は、今の若者世代とも、私たちとも違う。
ユウスゲのメンバーから、私はその「歌の歴史」を知り、多くのことを学んできた。

真夏の日差しに負けることなく、仲良く房になって支え合い、風に揺れるサルスベリのように仲間と歌うことを生きがいにしている人たちがいる。
その心の輝きを、いつまでもいつまでも持ち続けて欲しい。。
白く眩しいサルスベリのように、愛敬の歌声を響かせながら。。。
続きを読む
2020年04月29日
コンサート『Salon de Musique vol.2 』開催日程延期のお知らせです。
コンサート延期のお知らせです。


2020年度県民協働企画事業
コンサート『Salon de Musique vol.2 -音楽とトークとスイーツと-』の開催延期をお知らせします!
7月5日(日)、滋賀県立文化産業交流会館小劇場を会場に、14時開演(13時30分開場)を予定しておりました『Salon de Musique vol.2 -音楽とトークとスイーツと-』は、新型コロナウイルスの感染拡大防止を考慮し、延期することになりました。
振替公演は、2021年3月6日(土曜日)午後似地開演となります。
チケット販売日は、12月12日(土曜日)午前10時からとなります。
新型コロナウイルスの感染については、まだまだ心配が尽きませんが、「人間の持つ力」を信じ、協力と思いやりで一日も早く「自由に楽しみ」「自由に歌い演奏できる」世の中を取り戻せる日を願うことが、いまの自分に出来ること信じます。
《八重桜 花言葉「ゆたかな教養」》

まるで疫病蔓延の原因のように騒がれた「さくら」。
日に日に話題は消えゆき、花びらの散った桜の木を座り込んで撮影する人は、もう居なくなりました。
今、山桜は遠くの景色を彩り、八重の桜がアチラコチラに咲いています。
私達は来年の今頃、いまの辛さを忘れたかのように家族と、仲間と笑い合っているのでしょうか。
それとも、今よりも更に「我慢」「辛抱」「忍耐」を突きつけられているのでしょうか。
「戦争中はこんなもんやなかったよ。」
母がもし側にいたら、元気を無くしそうな私に、そう言って延々と子供の頃の話を聞かされたでしょう。
忘れたいこと。
忘れなくてはいけないこと。
忘れてはいけないこと。
このことを心で感じられる「教養」について考える時間を、音楽家として大切にしたいと、美しく優しく八重に咲く桜を見ながら思いました。。
2020年04月08日
コンサート『Salon de Musique vol.2 』チケット販売見合わせのお知らせ。
チケット販売見合わせのお知らせです。

2020年度県民協働企画事業
コンサート『Salon de Musique vol.2 -音楽とトークとスイーツと-』のチケット販売見合わせのお知らせです。
7月5日(日)、滋賀県立文化産業交流会館小劇場を会場に、14時開演(13時30分開場)を予定しておりました『Salon de Musique vol.2 -音楽とトークとスイーツと-』は、新型コロナウイルスの感染拡大が収束していないことから、当面の間チケット販売(4月11日〜)を見合わせることにいたしました。
チケット販売日および公演実施の有無(延期等を含む)については、順次お知らせさせていただきます。
私があたためてきたこの企画は、決してなくなりません。
お客様、仲間とスタッフがのびのびと音楽を楽しめる環境はきっと来ます。
その時まで、お楽しみは大事にとっておきましょう。
滋賀県でも感染者数が着実に増えている今、自分にとって、周りの人にとって「何をすることが大事か」を真剣に考える時だと考えます。
「焦り」「不安」「怒り」・・・
人間の弱さを見透かすように、コロナウィルスはこの3つを武器にして、平和な時代を生きてきた私達に対し、「自身と戦う強さ」がどれくらいあるかを試しているように思えてなりません。
そしてこの、「焦りウイルス」「不安ウイルス」「怒りウイルス」を発症させる原因となる、最も手に負えないウイルスが、「無神経ウイルス」です。
「無神経ウイルス」に効くワクチンは今の所ありません。
でも、「勇気」という免疫は、一人より二人、二人より三人と、地域・国レベルで強くなると思うのです。
勇気=正しい判断・行動力
そのことをいつも頭において考え、行動したいと思っています。
新型コロナウイルスの感染によって、知らず知らずに心を病んでいる人もいます。
私自身もそうかもしれません。
良い意味でも、悪い意味でも、心には目に見えるメモリがないのです。
新型コロナウイルス感染者に効くワクチンを待ちつつ、個々の「勇気免疫体」を増やしていきましょう。
そう・・・笑顔、えがお、EGAO。。。

《2018年 春》
2020年03月25日
「Salon de Musique-音楽とトークとスイーツと-」 Vol.2 & 今後の湖音活動について。
昨年開催しましたコンサート「Salon de Musique-音楽とトークとスイーツと-』 Vol.2 (県民協働企画事業)開催のお知らせです。
第2回目となる今回は、マリンバや打楽器を加え、華やかなパリから世界へと広がる演奏曲目でプログラムを構成しました。
パリで活躍した音楽家を中心に、フランスからアメリカ、スペイン、アルゼンチンなど、作曲家たちのルーツや音楽について語りながら、歌とサックス、マリンバ、ピアノによるソロやアンサンブルでステージを彩ります。
今回のスイーツは、私も大好きな長浜の Ichigo ichiE(イチゴイチエ)さんのお菓子です。
また、コンサート開演前(13:00-13:20)には、ラ・ルミエールによるウエルカム・コンサートをロビーにて開催します。
初夏の午後のひとときを、フランスゆかりの音楽とお菓子でお楽しみください。


◆コンサートに伴う今後の湖音の対応について 大切なおしらせ◆
昨年の7月、満席のお客様を文化産業交流会館におむかえし開催した1回目。
このときには出演者もお客様も、今の状況を想像すらしていなかったと思います。
新型コロナウイルス(COVID-19)の感染が確認されたのは、コンサートからわずか5ヶ月後の12月でした。
その時は知識も不安もなく、おそらく私も含め多くの人は「他人事」のような感覚であったのかもしれません。
コンサートや多種なイベントは大きな影響を受けています。
音楽業界だけでなく、「思うように(まったく)仕事ができない。」「思うように病気の治療が出来ない。」など、多くの人が近年経験したことのない不自由さや憤りを感じています。
今後、私のブロブでお知らせしたコンサートにおいて、延期や中止の判断がなされた場合、お客様に御迷惑をおかけしないよう、主催者が責任を持って対応します。このコンサート企画は決してなくなりません。
また、出演者全員でのリハーサルや、ラ・ルミエールによるウエルカム・コンサートの練習においても、限られた空間の中で人が寄り、コミュニケーションをとるいう点で、今後の新型コロナウイルス感染の経過をみながら、慎重に判断させていただきます。
企画者として、共演者やコーラスのメンバーを不安にさせないことも大きな責任の1つと私は考えています。

◆ラ・ルミエールのメンバーへ◆
みなさんに会えない寂しさを、日々感じて過ごしています。
「自粛」と「我慢」。
どちらも自主的であり、どちらも受け身的ですね。
「歌うこと」は「話すこと」よりも、人への病気の感染力は強いように思います。
また、喉を潤すためのお茶やミネラルウォーターを口に含むことで、その分拡散されるものも多くなります。
よく言われている、「人と人との距離を開ければいい」という不確定で無責任な認識は、病気を拡大させるもとです。
お仕事の合間をぬって練習に通ってくれるメンバー。
家族の介護をしながら、時間を作ってさんかしてくれるメンバー。
仲間のことを絶えず思い、ムード作りを欠かさないメンバー。
早くみんなで歌いたいですね。
4月のにメンバー専用のyoutubeで、曲について、練習について、そして楽曲のポイントについて配信する予定ですので、グループLINEを楽しみに待っていてください。もちろん、私からのメッセージ付きです。
今うたえなくても、必ずうたえる時が来ます。
だから、今は自分と向き合って、自分と二人きりで歌ってみてください。
小さな声で構いません。
自分の声だけに耳をすませてみてください。

歌を愛する人のもとから、歌は決して離れてはいきません。。。
第2回目となる今回は、マリンバや打楽器を加え、華やかなパリから世界へと広がる演奏曲目でプログラムを構成しました。
パリで活躍した音楽家を中心に、フランスからアメリカ、スペイン、アルゼンチンなど、作曲家たちのルーツや音楽について語りながら、歌とサックス、マリンバ、ピアノによるソロやアンサンブルでステージを彩ります。
今回のスイーツは、私も大好きな長浜の Ichigo ichiE(イチゴイチエ)さんのお菓子です。
また、コンサート開演前(13:00-13:20)には、ラ・ルミエールによるウエルカム・コンサートをロビーにて開催します。
初夏の午後のひとときを、フランスゆかりの音楽とお菓子でお楽しみください。


◆コンサートに伴う今後の湖音の対応について 大切なおしらせ◆
昨年の7月、満席のお客様を文化産業交流会館におむかえし開催した1回目。
このときには出演者もお客様も、今の状況を想像すらしていなかったと思います。
新型コロナウイルス(COVID-19)の感染が確認されたのは、コンサートからわずか5ヶ月後の12月でした。
その時は知識も不安もなく、おそらく私も含め多くの人は「他人事」のような感覚であったのかもしれません。
コンサートや多種なイベントは大きな影響を受けています。
音楽業界だけでなく、「思うように(まったく)仕事ができない。」「思うように病気の治療が出来ない。」など、多くの人が近年経験したことのない不自由さや憤りを感じています。
今後、私のブロブでお知らせしたコンサートにおいて、延期や中止の判断がなされた場合、お客様に御迷惑をおかけしないよう、主催者が責任を持って対応します。このコンサート企画は決してなくなりません。
また、出演者全員でのリハーサルや、ラ・ルミエールによるウエルカム・コンサートの練習においても、限られた空間の中で人が寄り、コミュニケーションをとるいう点で、今後の新型コロナウイルス感染の経過をみながら、慎重に判断させていただきます。
企画者として、共演者やコーラスのメンバーを不安にさせないことも大きな責任の1つと私は考えています。

◆ラ・ルミエールのメンバーへ◆
みなさんに会えない寂しさを、日々感じて過ごしています。
「自粛」と「我慢」。
どちらも自主的であり、どちらも受け身的ですね。
「歌うこと」は「話すこと」よりも、人への病気の感染力は強いように思います。
また、喉を潤すためのお茶やミネラルウォーターを口に含むことで、その分拡散されるものも多くなります。
よく言われている、「人と人との距離を開ければいい」という不確定で無責任な認識は、病気を拡大させるもとです。
お仕事の合間をぬって練習に通ってくれるメンバー。
家族の介護をしながら、時間を作ってさんかしてくれるメンバー。
仲間のことを絶えず思い、ムード作りを欠かさないメンバー。
早くみんなで歌いたいですね。
4月のにメンバー専用のyoutubeで、曲について、練習について、そして楽曲のポイントについて配信する予定ですので、グループLINEを楽しみに待っていてください。もちろん、私からのメッセージ付きです。
今うたえなくても、必ずうたえる時が来ます。
だから、今は自分と向き合って、自分と二人きりで歌ってみてください。
小さな声で構いません。
自分の声だけに耳をすませてみてください。

歌を愛する人のもとから、歌は決して離れてはいきません。。。
2020年02月27日
式歌の意味。。。
小・中学校、高等学校の卒業式歌はさまざまで、
その学校の伝統を守り歌い継がれているものや、
年ごとに先生や生徒の思いや工夫によって変わる場合もある。
卒業生にとって、
ともに過ごした友達と最後に声を合わせる卒業式歌は、
特別なものであってほしいといつも思う。
式歌の指導に入ると、
その学校の生徒の様子や先生の一生懸命さは、
手にとるようにわかる。
「歌」は、
それだけたくさんのものを映し出す力を持っているから。
声帯を通った息は体に支えられて「顔(口)」で最後の仕上げをし外に出される。
「眼」「頬」「鼻」「口」それぞれが声を色づけていく。
そして大勢のそれが一つになる。
今日は、
米原市立柏原中学校に出かけた。
全校生徒を合わせても60名に満たないこの学校には、
文化祭の全校合唱指導にも入っている。
殆どの中学校が「コンクール」という競いの中で合唱をする中、
この学校では1年から3年までが一つになって曲を仕上げる。
文化祭を楽しみにしている自分たち、
その姿をたのしみにやってくる家族や地域の人のために頑張るのだ。
その「こころ」は、
勝ち負けを意識して練習を始めるのとは、
きっとスタートから少し違うかもしれない。
今年の式歌は『友〜旅立ちの時』(北川悠仁 作詞・作曲/相澤直人 編曲)。
リズムを大勢で揃えるのがひとつの課題だが、
言葉を大切に理解しながら歌うと、
不思議と少しずつそろってくる。
生徒たちの素直さは、
曲の仕上がりをうんと早くする。
「vocaliseは卒業生ひとりひとりがそこにメッセージを込めよう。単なる母音ではないからね。」
わたしの呼びかけに数人の女子がニッコリ微笑んだ。
授業がおわるころには倍の声が出ていた生徒たち。
この子達が卒業式歌の意味を噛みしめるのは、
うんとうんと先かもしれないが、
どうかその素直な瞳と声で、
あなたたちの卒業式を飾って欲しい。。。